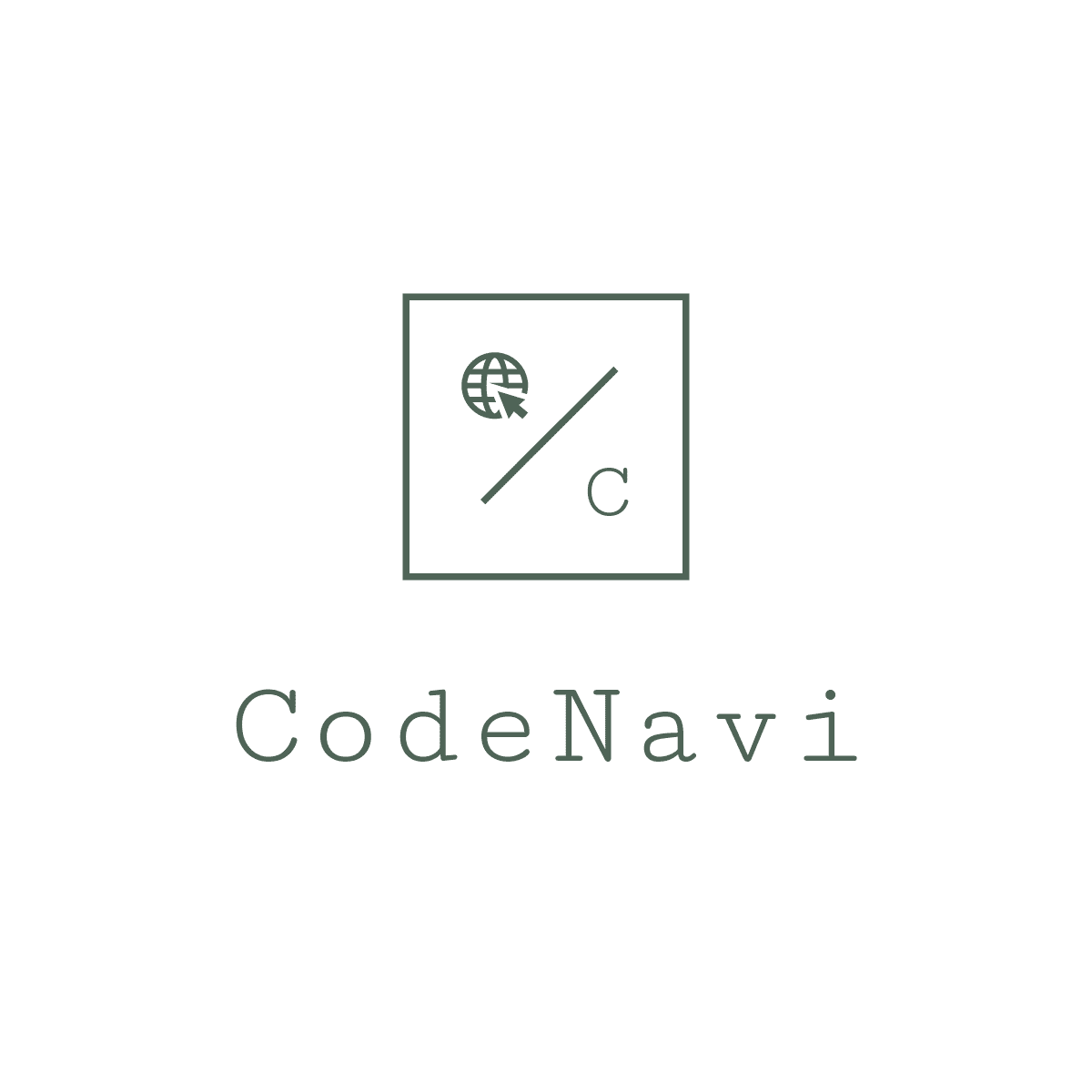問1 ITを活用した業務改革について
近年は、ITの進展によって、事業課題に対してITを積極的に活用し、新たな事業・
サービスを展開することが可能になっている。このような中、ITストラテジストは、
事業部門と協力して、ITを活用した業務改革を実施することによって、事業・サービ
スの優位性確保、新規顧客の獲得などの事業課題に対応することが求められている。
ITを活用した業務改革には、例えば、次のようなものがある。
・外勤業務サービスの差別化のために、営業員、サービス員にタブレット端末な
どのスマートデバイスを配備し、業務進捗状況の迅速な確認、顧客別情報の適
時適切な提供などの業務改革を行い、顧客対応時間の増加、顧客サービスの強
化を推進する。
・店舗の売上げ拡大のために、内部のPOS情報、外部のSNS・ブログの情報を活
用した顧客の購買傾向の分析と的確な品ぞろえ、対象を絞り込んだ顧客への情
報発信などの業務改革を行い、販売機会の創出、顧客の囲い込みを推進する。
・物流サービスの優位性確保のために、配送車両にGPS端末と各種センサを配備し、
位置確認、道路情報に基づく配送経路の柔軟な変更、顧客への的確な情報提供な
どの業務改革を行い、顧客満足度の向上、物流サービスの品質向上を推進する。
ITストラテジストは、ITを活用した業務改革を実施する際、事業課題に関連する業
務の現状と将来見通し複数の改革案と各案の効果の比較、活用するITの費用などを
検討し、定量的な費用対効果の根拠を示して経営者に説明することが重要である。
あなたの経験と考えに基づいて、設問ア〜ウに従って論述せよ。
設問ア あなたが携わった、ITを活用した業務改革について、業務改革の背景にある
事業課題を、事業の概要、特性とともに、800字以内で述べよ。
設問イ 設問アで述べた事業課題に対応するために、実施した業務改革とそのときに
活用したIT、及び費用対効果の定量的な根拠とそのときに検討した内容につい
て、800字以上1,600字以内で具体的に述べよ。
設問ウ 設問イで述べた業務改革の実施結果は、経営者にどのように評価されたか。
更に改善する余地があると考えている事項を含めて、600字以上1,200字以内で
具体的に述べよ。ここまで問題。ここから答案。
IT企画室の課長として2017年に担当した、見込み顧客管理システムへの地図UI導入を通じた受注率向上施策について論じる。
第1章.ITを活用した業務改革の背景
1ー1.事業の概要と特性
A社は、国内4大都市圏で、単身用賃貸マンションを中心に建設営業を展開するマンションメーカーだ。私はA社のIT企画室に所属するITストラテジストだ。
A社の年商は1200億円、従業員数は1400名で、うち半数の700名は営業社員である。特徴は飛込み中心の営業スタイルだ。10階建て前後の受注が中心で、単価は4億円程度。年商1200億円は受注300件で構成している。
2017年は5年間の中期経営計画(以下、中計)の初年度で、計画における5年後年商目標は1600億円であった。近年伸びている「法人向け・居住用以外の強化」というマイナーテーマはあるものの、経営基本方針は既存製品、既存市場での市場浸透戦略である。マーケティングに関しても、コーポレートサイトのリブランディング・SEO強化を通じた問合せ増加などのサブ施策は打つが、主軸は営業社員による飛込み営業を継続する方針だ。
1ー2.背景にあった事業課題
A社の中計達成に向けた事業課題として、特に営業面では品質と効率、両面の向上が必要であった。
品質においては入り込み強化が重要だった。類似した状況の見込み顧客に対しても、提案に繋げられる社員と繋げられない社員が存在し、営業ノウハウの共有や過去提案情報の有効活用を促進して、営業部全体の提案力を引き上げる必要について、経営から指摘されていた。
効率においては有効面談数の増加が重要だった。営業支援システムがモバイル対応しておらず、出先で効率良い訪問ルート検討や、飛込み直前の情報確認ができず、帰社後の訪問記録登録も業務効率を落としていた。
第2章.業務改革の実施
2ー1.営業業務の現状と将来見通し
前述した事業課題への対応の為、中計初年度に営業支援システム(以下、SFA)の改修も視野に入れた営業業務改善を予定していたが、具体的な内容は未定であった。そこで私は、当該改善の具体化に向けて、営業本部と検討を開始した。
営業本部との打ち合わせで見えてきた現状と将来見通しは以下の通りであった。
①KPIの状況
全社年間で、訪問150万件、本提案権獲得(以下単に提案率)0.2%、提案3000件、受注率10%、受注300件、平均受注高4億円、年商1200億円の構成である。
②改善可能性の見通し
訪問件数、受注率、平均受注高の改善は難易度が高い一方、提案率は改善余地が大きい。
例えば提案率が倍の0.4%に上げられれば、仮に訪問が100万件に落ちても、提案件数は4000件となり、年商1600億円達成可能。
③提案率向上の重要成功要因
SFAの利便性向上を通じた情報充実化と利用率改善。出先でモバイル端末(以下、スマホ)から登録・閲覧できることが最低条件。
2ー2.複数の改革案と活用したIT
上記の見通しを受け、まず私は2通りの改革案を挙げた。
・案A:SFAを単にレスポンシブ化する
・案B:SFAをバックエンドとして利用するスマホアプリを新規構築し、これまでになかった地図型UIも導入する
案AとBについて営業本部の意見を伺った所、これまでの単なるフォーム型で住所管理するのではなく、地図型UIで見込みの地点管理を出来ることは、利用率向上に大きく貢献するはず、ということであった。そこで、案Bで企画を進めることとした。案Bでは、「GPS登載のスマホ」「地図サービスのAPIを利用するネイティブアプリ(クローズド・ビジネスユース)」が、案AにはないIT要素として考慮必要であったが、既に他社先行事例を調査済みで、実現可能性に懸念はなかった。そこでRFPをまとめ、複数の開発会社に提案依頼を行い、X社に開発委託する段取りを行った。費用は一式で初期1500万円、サーバ費用等を含めた年間運用保守費300万円、5年計3000万円だった。
なお、「スマホアプリを作るならプッシュ通知も実装できるか」という意見が営業本部から出たが、希望する通知の内容は具体化されておらず、仕様策定に時間を要しそうだったので、今回はクイックウインズを目指そう、と提案して意見の集約を行い、当該仕様は除外して進めることとした。
2ー3.稟議申請、承認と改革の実施
当該開発費用の稟議起案に当たり、企画が中計、全体システム化計画に整合しており、費用対効果の目算が立っている点を資料に整理した。特に費用対効果に関しては、5年間の外部費用が3000万円であるのに対し、狙う効果は提案率倍増(0.2→0.4%)を通じた年商+400億円であった為、承認された。
なお、本開発が提案率倍増に寄与できる理由は、以下を明示した。
・これまでPCでしかSFA操作ができなかった
・これからはスマホでSFAが閲覧登録可能
・これまでリスト、フォームしかなかった
・これからは地図型UIでも閲覧登録可能
・SFA利用率があがり、見込み情報、過去提案情報が更に充実化する
・結果として、より提案に繋がりやすい見込み先への重点訪問、適切な会話糸口の発見等を通じた提案率向上が狙える
・他効果として、主権者在宅時間の確認を通じた訪問ルートの最適化も見込める
2017年6月に開発着手し、11月末に新SFAマップアプリをリリースし、12月に営業支店向け説明会を複数回開催してオンボーディングを行い、1月~3月を初期測定期間とした。
第3章.改革実施結果の振返り
3ー1.経営者への報告
2018年1月から3月の初期測定期間終了後、本件開発を通じた業務改革についてレポートをまとめ、期初の中計進捗役員会で経営への報告を行った。プレゼンテータは営業本部長に担っていただいた。
報告の場には、工事部、設計部などの技術担当役員や、営業系以外の管理部門の部長等も出席されていたため、レポートでは、取り組みの背景や狙いを省略せず、初見の方にも伝わる資料構成を意識した。
実施結果本論では以下を示した。
①KPIの状況
全社4Q実績で、訪問30万件、提案率0.3%、提案900件、受注率10%、受注90件、平均受注高4億円、売上360億円を達成。
②成功要因分析
・旧SFA時代のデータを無駄にせず、緯度経度変換をして1月からマップ閲覧可能とした
・訪問記録件数が、リリース時15万件にたいして計測終了時点20万件で、一気に伸びた
・これまで帰社後に行っていた訪問履歴登録は出先で半分は済むようになり、帰社後の必要時間が半分以下になったため、提案記名をいただくために自主的に作成する独自の商圏分析資料(〇〇駅前再開発に伴うエリア価値向上、△△社支社開設に伴う単身賃貸へのニーズ向上、などを各支店で独自に作成する)に使える時間が増えた
・営業本部から営業部に粘り強いオンボーディングを計測期間中も実施した
・IT企画室は開発会社と共働し、半年間でのSFAの改善開発を遅滞なく完遂した
3ー2.経営からの評価と改善余地
経営からの評価は好評だった。特に中計の初年度に、A社が大切にしている「飛込み営業」に関する業務プロセスの改善を、営業本部とIT企画室が協力してやり遂げた点に、ありがたいおほめの言葉をいただけた。
営業支援領域における更なる改善余地に関しては、資料後半にて自主的に触れた。その内容は、「訪問記録の全文検索機能追加」である。コーポレートサイトのSEO強化案件を通じ、キーワードから流入意図を探る方法をIT企画室として内部化、定着化できてきていたため、これを応用して、営業社員のニーズをSFA検索履歴から探り、販促チラシやセミナーの企画に活用できないか、と考えたものだ。当内容についても、中計進捗役員会のその場で経営の賛同をいただけたため、実際に開発を進めた。
2022年現在、マップ型SFAアプリ、及びSFA検索履歴を使ったインターナルマーケティングは、双方順調に運用中である。目標であった1600億円は昨年度達成することができた。
以上